- 更新日: 2025年03月27日
- 公開日: 2025年03月27日

目次
給与明細は従業員に支給した賃金の根拠となる大切な書類です。基本給や残業代などの支給額だけではなく、社会保険料や税金などの控除額や、労働日数や残業時間数などの勤怠についても確認できる書類となります。企業側も従業員側も、ある程度の期間は給与明細を保管しておくことがおすすめです。
この記事では、給与明細の保管義務や保管期間に関する情報、保管しておくメリットなどを徹底解説します。また、書類の効率的な管理におすすめのサービスもご紹介するため、給与明細の保管についてお悩みの担当者様は、ぜひ参考にご覧ください。
目次
給与明細に保管義務や保管期間はある?
給与明細には法律によって決められた保管期間が存在するのでしょうか。以下では、給与明細の保管義務・期間などについてご紹介します。
給与明細の保管義務は?
所得税法により、会社側が給与を支払う際は、給与明細書を発行することが義務付けられています。保管についてのルールはないため、たとえ発行直後に控えを破棄したとしても法律上は問題ありません。ただし、給与明細の作成に必要となる従業員の情報に関しては、記帳方法や保管期間、保管方法などが定められています。
また、給与明細を受け取った従業員側にも、保管する義務はないとされています。しかし、個人で確定申告を行う場合や、収入の証明を行う場合などは、給与明細が必要になるケースがあります。念のために保管しておくと安心です。企業側は、従業員に対して一定期間は保管しておくよう指導することが求められます。
給与明細に関する書類の保管期間は?
給与明細に関連する書類については、労働基準法や国税通則法によって定められた保管義務があります。例えば、労働基準法では労働者名簿や賃金台帳、出勤簿、賃金関連書類、雇用関連書類、災害補償(労災)関連書類などの書類を5年間保管することが定められています。そのうち、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は「法定三帳簿」と呼ばれる重要書類です。ただし出勤簿については記載項目などの規定はなく、タイムカードや勤怠管理システムなどを使用するケースも見られます。
国税通則法では、源泉徴収簿や給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などを7年間保管することが決められています。上記の書類を従業員ごとに保管しておくためには、相応のスペースが求められます。書類管理の手間が増えてしまう点も考慮する必要があるでしょう。
【出典】厚生労働省:改正省令による改正後の労働時間等の設定の改善に関する法律施行
規則(15ページ) URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf
【出典】国税庁:給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2503.htm
給与明細を保管する理由
給与明細の保管は義務ではありませんが、しばらく保管しておかなければトラブルにつながるリスクがあります。以下では、給与明細を保管しておいたほうが良い理由について、企業側と従業員側それぞれの視点で解説します。
企業側の保管理由
従業員から再発行を依頼されることがあるため
従業員が給与明細を紛失してしまった際、再発行依頼を受けることがあります。企業側が給与明細の控えを破棄していた場合、勤怠情報などをもとに一から給与計算する必要があります。手間が増えてしまうのはもちろん、操作ミスや計算ミスなどが起こると、前回発行したものと金額の異なる明細になってしまう可能性があるでしょう。控えを保存しておけば、最初に交付したものと同じ給与明細をスムーズに発行できます。
給与を支払った証拠となるため
給与明細書は、給与支払いの証明となる書類です。従業員側から未払い賃金の請求を受けるといったトラブルが起こった際も、証拠書類として給与明細を出すことができます。万が一の場合を想定し、保管しておいたほうが良いでしょう。
従業員側の保管理由
収入証明書として必要になるケースがあるため
住宅・自動車などの高額な買い物でローンを組むときや、クレジットカードを作成するときなどは、手続きの際に収入証明書の提出が必要になるケースがあります。給与明細は毎月の収入を証明できる書類です。源泉徴収票がない場合の代用として使用することもあれば、源泉徴収票と給与明細を併せて提出するパターンも見られます。数カ月分の給与明細を求められることもあるため、一定期間分は残しておいたほうが良いでしょう。
転職の際に提出を求められることがあるため
転職活動を行っているとき、転職先候補の企業から給与明細もしくは源泉徴収票の提示を求められるケースがあります。給与金額を決定する際、前職の支給額を参考にすることがあるためです。
また、給与明細には支給される基本給や手当、控除される健康保険料や雇用保険料、厚生年金などのほか、勤務日数や欠勤日数などの情報も記録されています。そのため、前職の勤務状況を正確に把握するための書類としても利用されます。
給与明細の保管方法
給与明細の保存方法として、紙の状態でファイリングする方法と、電子データとして保管しておく方法があります。両者の違いやそれぞれのメリットを把握した上で、自社に合う方法を採用しましょう。
ファイリングする
紙の給与明細の場合はファイリングして所定の場所に保管しておきます。ノートに貼る、専用のバインダーやファイルボックスに収納するなど、管理しやすい方法を選びましょう。書類の数が多く社内のスペースが足りない場合、倉庫をレンタルするケースも見られます。
また、紙で保管する場合は、経年劣化の防止策も必須といえます。変色や脱色で文字が消えてしまい、正確な情報が読み取れなくなる可能性があるためです。直射日光の影響がなく、風通しの良い場所を選んで保管しましょう。1~2年は紙で保管し、あとはデータ保管に切り替えて劣化を防ぐというように、紙とデータを併用するのも対処法の一つです。
データで保管する
紙の書類の場合、5年もしくは7年の保管期限を守るためには、ある程度の保管スペースが必要になります。給与明細を電子化し、PCやクラウドに保管すれば、上記の問題を解決できます。従業員から再発行依頼を受けたときも、電子データであれば目的の明細をすぐに検索して出力可能です。印刷代やインク代などのコストも削減できます。電子化によって、業務効率化や費用節減を実現できるでしょう。
給与明細の電子化とは?メリット・デメリットと注意点、導入の手順
給与明細は保管期間を決めて効率的に管理しましょう
給与明細を保管しなくても法律違反にはなりません。ただし、トラブルを予防するためにもある程度の期間は保存しておくことが推奨されます。また、給与明細の関連書類の中には、5年間もしくは7年間の保管が義務付けられているものがあります。従業員数が多ければ該当の書類も膨大な量になり、効率的な管理が難しくなることもあるでしょう。さらに、企業が保管すべき書類は他にも多くの種類があります。必要書類の保管・管理業務に頭を悩ませるケースは少なくありません。
書類保管の問題を解決したい方におすすめなのが、寺田倉庫のハイブリッド文書倉庫「CLOUD CABINET」です。一つのシステム上で、紙の契約書・電子契約・スキャンした文書を一元管理することができます。紙の原本を寺田倉庫へ保管しておき、必要に応じてすぐに電子化するといった対応も可能です。詳しいサービス・機能について気になる際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
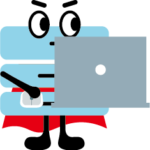
CLOUD CABINET編集部
文書管理に役立つ情報を発信していきます。 当編集部は、文書情報管理士・文書情報マネージャーなどの有資格者で構成されています!






