- 更新日: 2025年03月28日
- 公開日: 2025年03月28日

目次
取引先と紙の請求書でやり取りする工数が多く、毎月の請求業務で大きな負担となっていないでしょうか。紙ベースの請求業務は発行側・受領側の双方の企業にとって負担となります。近年は、こうした請求業務の課題解決へ向けて、電子化を推進する動きが見られます。
本記事では、請求書を電子化するメリットや注意点を解説します。既存の請求業務を見直して効率化を実現するために、ぜひ参考にお読みください。
目次
請求書の電子化の概要
初めに、近年のビジネスシーンで請求書の電子化が求められる理由を解説します。また、請求業務で用いられる電子請求書の種類をご紹介するため、電子化後の事務処理の参考にしてみてください。
請求書の電子化が必要な理由
近年は、電子帳簿保存法に対応して、請求書の電子化を進める企業が多くなっています。業務効率化や生産性向上を目的として、経理業務のペーパーレス化・デジタル化・DX化を進めるケースも少なくありません。また、2024年10月以降の郵便料金値上げの影響から、コスト削減のために紙ベースの運用を見直す企業もあります。こうしたさまざまな理由から、請求書の電子化が進められている状況です。
【出典】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdfhttps://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html
電子化された請求書の種類
経理業務では、一般的に以下のような種類の電子請求書を取り扱う可能性があります。
| ・メールなどで電子データとして送受信した請求書 ・電子帳簿保存システムで送受信した請求書 ・Webサイト上にアップロードされた請求書 ・紙の書類をスキャンして電子化した請求書 |
メールなどで電子データとして送受信した請求書
発行側が請求書データをメールに添付して送付するケースです。電子帳簿保存法の保存区分は「電子取引」に該当し、電子保存が義務化されています。
電子帳簿保存システムで送受信した請求書
発行側が電子帳簿保存法に対応した専用システム上で請求書データを送信するケースです。電子帳簿保存法の保存区分は「電子取引」に該当し、電子保存が義務化されています。
Webサイト上にアップロードされた請求書
発行側が請求書データをクラウドサービスなどにアップロードして共有するケースです。受領側は請求書データをダウンロードして受け取ります。電子帳簿保存法の保存区分は「電子取引」に該当し、電子保存が義務化されています。
紙の書類をスキャンして電子化した請求書
電子帳簿保存法では、発行側が紙で請求書を送付した場合、受領側が紙と電子データのどちらの形式で保存するか選択できます。原本や控えをスキャンして電子データとして保存することが可能です。電子帳簿保存法の保存区分は「スキャナ保存」に該当します。
請求書を電子化するメリット
請求書を電子化すると、発行側・受領側の企業はそれぞれどのようなメリットが期待できるのでしょうか。ここでは、電子化のメリットを解説します。
請求書を電子化し発行する側のメリット
請求書の印刷や郵送にかかるコストを削減できる
紙媒体の請求書を発行する際、紙代・インク代・切手代などの費用が発生します。電子化すればこれらの経費を削減可能です。また、書類の封入など手作業の工数が減ることで、発送に関わる人件費を抑えられる可能性があります。
再発行などの対応が容易になる
電子請求書は、修正や再発行の対応を効率的に行えるのに加えて、請求データをタイムラグなく送付可能です。取引先や金額などの条件を指定して、発行済みの請求書を簡単に検索できるため、必要な情報を速やかに入手できます。
電子化した請求書を受領する側のメリット
請求書管理の効率化を図ることができる
電子請求書の受領側は、原本の保管スペースを削減し、文書の整理にかかるコストを抑えることが可能です。社内の無駄なスペースを無くし、ファイリング作業の時間と手間を削減することで、請求管理の効率化を実現できます。
請求書の受領から処理までの時間に余裕ができる
請求業務が電子化されると、取引先の発行業務の時間が短縮され、さらには郵送によるタイムラグがなくなります。結果として、受取側は請求書の受領から処理までの時間に余裕ができ、支払いスケジュールを調整しやすくなるのがメリットです。
発行する側・受領する側に共通するメリット
業務の効率化
請求書を電子的に発行・受領すると従来よりも取引の効率化を図ることができます。発行から受領までに発生する業務負担が軽減され、郵送のタイムラグがなくなるため、大幅な業務効率化を実現可能です。
経理担当者のテレワークが可能になる
電子請求書は、書面を紙で出力したり、担当者の印鑑を押したりする必要がありません。また、取引先とオンラインでやり取り可能です。出社が不要で、経理担当者のテレワーク(在宅勤務)を推進できます。
請求書の検索性の向上
請求書の電子データは、条件を指定して検索可能です。紙の請求書と比較して検索性が向上します。さらに検索性を向上させるなら、高度な検索機能を搭載した請求書発行・管理システムを導入するのが有効です。
請求書を電子化する際の注意点
請求書の電子化では、発行側・受領側それぞれが注意したいポイントや、両者に共通する注意点があります。最後に、請求書を電子化する際の注意点をお伝えします。
請求書を電子化し発行する側の注意点
紙の請求書が必要な場合への対応
発行側が電子帳票を導入しても、取引先が紙の帳票を求める場合は、個別に紙で対応しなければなりません。その際、紙の請求書と電子請求書が混在し、請求業務が煩雑になるおそれがあります。
請求書の電子化について取引先の同意を得る必要がある
請求書の電子化にともない、事前に全ての取引先へ連絡し、承認を得る必要があります。その際、押印の必要性や、紙で対応する必要性があれば、取引先の希望に沿った対応が求められます。
発行フローの移行が必要
電子化への移行準備として、社内で請求書発行のルール設定やマニュアル作成を行う必要があります。専用システムの導入時は、既存の業務フローが変更され、新たな運営体制への移行に時間がかかる可能性も考えられるでしょう。
請求書発行システムを導入する場合は費用がかかる
請求書発行システムを導入するには、初期費用や月額費用を負担することになります。複数のシステムの費用面や機能面を比較検討して、自社に適したタイプを選定することが重要です。
電子化した請求書を受領する側の注意点
電子請求書の受領や管理するための運用ルールを決める手間がかかる
受領側は、受け取った請求書のデータを法的なルールに則って保存しなければなりません。電子帳簿保存法などの要件を満たす環境を用意し、請求管理のための体制や人員を確保する必要があります。
発行する側・受領する側に共通する注意点
セキュリティ対策が必要
請求書を電子的にやり取りする場合は、発行側・受領側ともに安全にやり取りする仕組みを構築しましょう。具体的には「メール送信時は宛先確認を徹底する」「請求書ファイルにパスワードを設定する」「改ざんできないデータ形式で発行する」といった対策が挙げられます。
一定期間の保存義務がある
請求書は、法人税法・所得税法・消費税法などの法律で一定期間の保存義務がある書類です。法人は、発行・受領した証憑書類を原則7年間保存する決まりとなっています。個人事業主は、基本的に5年間の保存が必要です。なお、インボイス制度に基づいて発行する適格請求書(インボイス)は、法人・個人事業主ともに7年間の保管が必要です。
請求書の電子化で発行側・受領側ともに効率化を実現可能
ここまで、請求書を電子化するメリットや注意点を解説しました。請求書を紙から電子データに移行すると、発行側・受領側ともに業務効率化を叶えられます。その際は、電子帳簿保存法などの法的なルールに適した保存方法を守りましょう。また、書類の電子化をスムーズに推進するなら、専用システムを活用する方法をおすすめします。
文書管理システム「CLOUD CABINET」は、契約管理の効率化に特化したシステムです。紙の契約書と電子データの両方をまとめて管理できるのが特長で、電子化への移行をサポートするサービスが充実しています。電子化にかかるコストや管理工数の削減につながるのが魅力です。サービスについて詳しくは以下のページからご覧ください。
契約書管理の効率化には「CLOUD CABINET」がおすすめ
この記事を書いた人
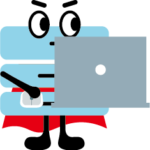
CLOUD CABINET編集部
文書管理に役立つ情報を発信していきます。 当編集部は、文書情報管理士・文書情報マネージャーなどの有資格者で構成されています!






