- 更新日: 2024年12月26日
- 公開日: 2024年12月16日
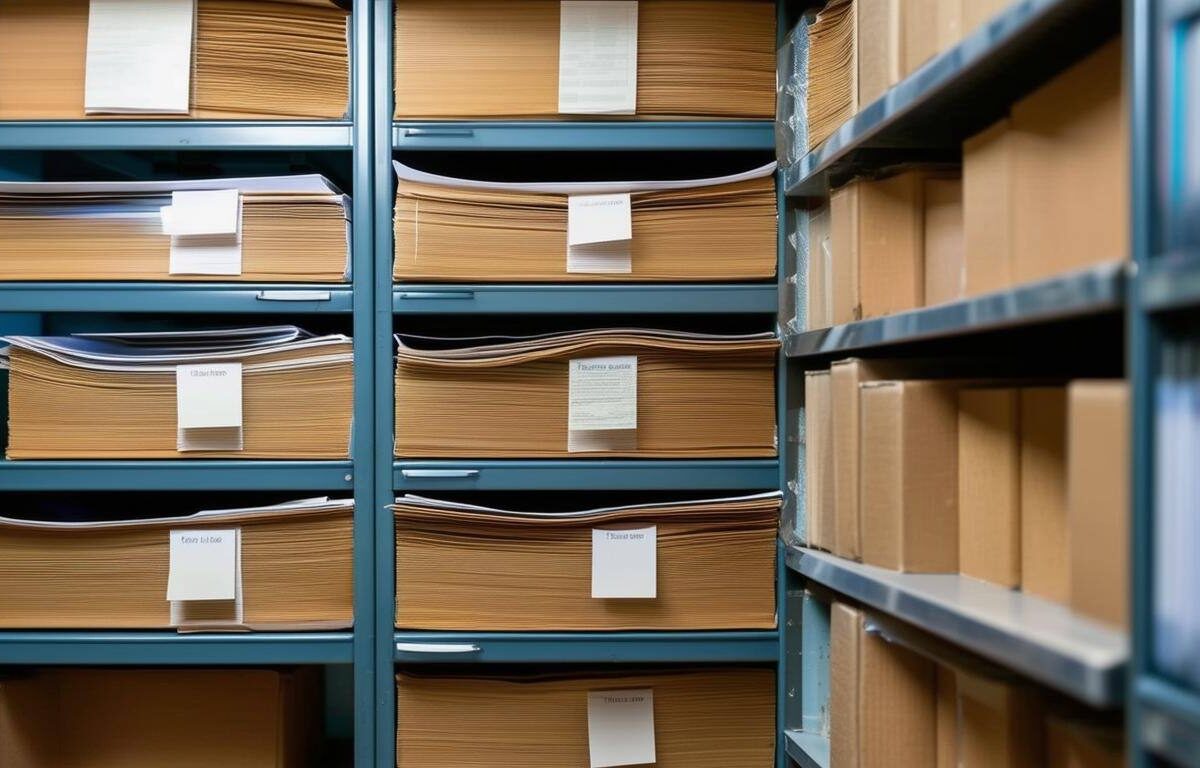
目次
現代の企業において、書類の管理は非常に重要です。書類の管理には「保管」と「保存」の二つの側面があります。これらの違いを理解し、適切に運用することで、業務の効率化やコンプライアンスを確保できます。この記事では、書類の保管と保存の違い、具体的な管理方法、およびそのポイントについて詳しく解説します。
目次
保管と保存の違い
書類の「保管」と「保存」には明確な違いがあります。これを理解することで、書類管理がより効果的になります。
書類の保管と保存の違い
書類の保管と保存の違いは、主に業務における使用頻度に基づいています。保管とは、業務で頻繁に使用する書類を管理することを指し、保存とは、ほとんど使用しないが法的に一定期間管理することが求められる書類を現状維持することです。
保管する書類の例
保管する書類には、よく使用する契約書や取引記録などがあります。これらの書類は、業務をスムーズに進めるためにすぐにアクセスできる状態で管理されるべきです。ファイル名やフォルダの分類を工夫し、必要な時に迅速に検索・アクセスできるようにします。
保管する書類の例
- 契約書
新規取引先との契約内容を確認するために頻繁に参照される。
契約更新時に過去の契約内容を確認する必要がある。
- 取引記録
売上や仕入れに関する記録は、経理部門で日常的に使用される。
監査や内部チェックの際にも必要となる。
- プロジェクト関連文書
プロジェクトの進行状況や計画を確認するために、チームメンバーが頻繁に参照する。
保存する書類の例
保存する書類には、法定保存文書などがあります。例えば、国税関係帳簿書類は、法律により一定期間保存が義務付けられています。これらの書類は、普段の業務では使用しないものの、必要な時に開示できるよう、適切に保存される必要があります。
法定保存文書の例
| 2年 | 健康保険・厚生年金保険に関する書類 (注)被保険者に関する書類は4年間保存。労働保険の徴収・納付に関する書類は3年保存 |
| 雇用保険に関する書類 | |
| 3年 | 労働者名簿 |
| 賃金台帳その他労働関係の重要書類 | |
| 雇入れ・解雇・退職に関する書類 | |
| 派遣元・派遣先管理台帳 | |
| 労災保険に関する書類 | |
| 労働保険の徴収・納付等の関係書類 | |
| 身体障害者等であることを明らかにすることができる書類 | |
| 3年 | 雇用保険の被保険者に関する書類 |
| 5年 | 従業員の身元証明書 |
| 誓約書等の書類 |
総務・庶務関連の法定保存文書
| 3年 | 四半期報告書 |
| 半期報告書・その訂正報告書の写し | |
| 5年 | 事業報告 |
| 有価証券届出書・有価証券報告書およびその添付書類 | |
| 産業廃棄物処理の委託契約書 | |
| 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し | |
| 10年 | 株主総会議事録 (注)本店備え置き分。支店備え置き分はその謄本を5年保存 |
| 取締役会議事録 | |
| 監査役会議事録 | |
| 監査等委員会議事録 | |
| 指名委員会等議事録 | |
| 製品の製造・加工・出荷・販売の記録 (注)民法では20年 |
経理・税務関連の法定保存文書
| 5年 | 監査報告 |
| 会計監査報告 | |
| 会計参与報告 | |
| 会計参与が備えおくべき計算書類、附属明細書 | |
| 7年 | 取引に関する帳簿 |
| 決算に関して作成された書類 (注)会社法で10年保存が義務がない書類以外 | |
| 現金の収受、払出、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引証憑書類 | |
| 取引証憑書類 | |
| 電子取引の取引情報に係る電磁的記録 | |
| 源泉徴収票(賃金台帳) | |
| 課税仕入等の税額の控除に係る帳簿、請求書等 | |
| 10年 | 計算書類および附属明細書 |
| 会計帳簿および事業に関する重要書類 |
書類を保管・保存する際のポイント
廃棄するタイミングを定めておく
書類を効果的に管理するためには、廃棄するタイミングを明確に定めておくことが重要です。不要な書類が積み重なり、オフィススペースを圧迫するのを防げます。保存期間を過ぎた書類を迅速に廃棄することで、書類整理が容易になり、必要な書類を探す手間と時間を削減できます。
ファイリング方法を工夫する
効果的な保管方法を導入することで、書類の管理が大幅に改善されます。使用頻度や担当者別に分類し、ラベルを貼ることで、必要な書類を迅速に取り出せるようにします。また、文書管理システムを利用することで、紙媒体の書類を電子化し、データとして管理することができます。
データで管理する
文書管理システムを利用して書類をデータ化することで、ペーパーレス化が進み、保管場所の問題が解消されます。電子化文書は、OCR技術を活用して文字認識を行い、検索性を高めることもできるのが利点です。また、クラウドストレージに保存することで、データのバックアップや災害時のリスク管理が容易になります。これにより、個人情報を含む重要書類も安全に保管できます。
社内に管理ルールを整備する
社内に統一された書類管理ルールを整備することで、全社員が一貫した方法で書類を取り扱うようになります。これにより、書類の紛失や重複を防ぎ、業務の効率化とセキュリティの強化が図れます。例えば、書類管理に関するマニュアルを作成し、全社員に周知徹底します。具体的な手順や注意点を明記し、定期的な研修を行うことで、書類管理の意識を高めます。統一されたルールの意味を全社員が理解し、原本や重要書類の適切な保管方法を守ることが大切です。
不要な文書を長期保存しない
不要な文書を長期間保存することは、スペースの無駄遣いやセキュリティリスクを増大させます。必要のない書類を整理し、定期的に廃棄することで、管理の負担を軽減し、より効率的な文書管理を実現します。書類の保存状況を定期的に見直し、不要な文書を廃棄するルールを社内で整備します。必要な書類が迅速に見つかる環境を維持できます。
デジタル化を進める
書類のデジタル化は、業務効率化とセキュリティ強化につながります。AIやRPAを活用して、書類処理の自動化を進めることで、手作業によるミスを減らし、業務をスムーズに行えます。また、電子署名やタイムスタンプを利用することで、デジタル文書の法的効力を確保し、改ざん防止を実現します。契約書などのリーガル文書も安心して管理できます。
セキュリティ対策する
電子化された書類は、適切なセキュリティ対策を講じることで、紙媒体に比べて高い機密性を保つことができます。アクセス権限の設定やデータの暗号化を行い、情報漏洩のリスクを最小限に抑えます。特に、法務部門が扱う機密文書の管理においては、セキュリティ対策が重要です。
関連法規の遵守する
書類の管理においては、関連法規の遵守が不可欠です。電子帳簿保存法やe-文書法に基づき、適切な保存要件を満たすことで、コンプライアンスを確保します。また、書類の保存期間を守ることで、契約書や取引内容に関する項目などを正確に記録・保管できます。
保管と保存の違いを理解し、適切な方法で管理
書類の管理は、企業の業務効率化やコンプライアンスの確保に直結する重要な課題です。保管と保存の違いを理解し、適切な方法で管理することで、書類の有効活用が可能となります。文書管理システムやデジタル化技術を活用し、効率的な書類管理を実現しましょう。具体的なソリューションとして、寺田倉庫のCLOUD CABINETは、書類の保管から電子化までを一気通貫でサポートする文書管理システムです。
この記事を書いた人
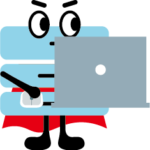
CLOUD CABINT編集部
文書管理に役立つ情報を発信していきます。 当編集部は、文書情報管理士・文書情報マネージャーなどの有資格者で構成されています!





