- 更新日: 2024年12月26日
- 公開日: 2024年12月26日

目次
契約の締結後、決められた期限までは契約書の保管が義務づけられています。会社法や法人税法などの法律を根拠とした保管期間が定められているため、違反にならないようしっかりと確認しておくことが重要です。契約書は適切な期間にわたり、ルールを守って保管しましょう。
この記事では、契約書の主な保管期間や保存方法、よくある疑問や回答などをご紹介します。契約書の保管・管理についてお悩みの方は、ぜひ参考にご覧ください。
目次
契約書の保管期間は何年か?
企業で取り扱う契約書には、法律上の保管期限があります。主な基準とされるのが会社法・法人税法・電子帳簿保存法です。ここでは、文書の保管義務や年数を解説します。
契約書の保管期間を定める主な法律
会社法
会社法第432条には、1項に適切な会計帳簿の作成について、2項に保存についての規定が記載されています。これにより、株式会社の事業に関する重要な資料は、10年間保管しておくことが義務づけられています。「事業に関する重要な資料」にあたる契約書については、10年の保管が必要です。
法人税法
法人税法とは、企業がその事業活動で得た所得に対して課される「法人税」について定めた法律です。法人税法施行規則の第59条には、税務関係の帳簿書類を7年間保管することが定められています。
法人税法施行規則とは、法人税法に沿った実務上の取り決めを細かくまとめたものです。ここで言う「帳簿書類」には契約書も含まれます。また、保管期間の起算日は、契約書の作成日ではありません。「作成・受領した日の属する事業年度の終了日翌日から2カ月経過した日」が起算日となります。
(例えば、事業年度が令和2年10月1日から令和3年9月30日の場合、令和3年11月30が起算日となり、この例における帳簿の保存期間は、令和10年11月30日までとなります)
電子帳簿保存法
PDFファイルのように、電子データの形式で作られた契約書の保管期間は、電子帳簿保存法によって定められています。電子帳簿保存法は国税関係帳簿書類の全部または一部を電子データにて保存することを認めた法律で、1998年に施行されました。
契約書を電子データで保管する場合の期間も、紙の契約書と同等のルールが適用されます。ただし、保存の際は一定の要件を満たす必要があるのがポイントです。
2022年1月1日施行の改正電子帳簿保存法では、各種要件の緩和・廃止が実施されました。契約書保管に関連する要件もいくつか変更されています。例えば、スキャナ保存の際に付与するタイムスタンプは、付与期限が延長されました。帳簿書類の保存についても、必須となる検索項目が削減されています。税務署長の事前承認なしに電子保存を導入できるようになったのも大きな変更点です。その他にも多岐にわたる要件があるため、ルールを守って保管できるように確認しておきましょう。
電子帳簿保存法について、詳しくは以下の関連記事で解説しています。
こちら→【e文書法と電子帳簿保存法の違いと電子化時の注意点】
主な契約書・文書の保管期間
| 保管期間 | 契約書・文書 | 法律 |
| 2年 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険に関する書類 | 健康保険法施行規則第34条ほか |
| 3年 | 労災保険に関する書類 | 労働者災害補償保険法施行規則第51条 |
| 労働保険の徴収・納付等の関係書類 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条 | |
| 派遣元管理台帳 | 労働者派遣事業法第37条 | |
| 4年 | 雇用保険の被保険者に関する書類 | 雇用保険法施行規則第143条 |
| 5年 | 会計監査報告 | 会社法第442条 |
| 有価証券届出書等の写し | 金融商品取引法第25条 | |
| 7年 | 領収書などの証憑類 | 法人税法施行規則第59条、第67条 |
| 請求書、契約書、見積書など | ||
| 電子取引の取引情報 | 電子帳簿保存法施行規則第8条 | |
| 源泉徴収簿(賃金台帳) | 国税法第70条、労働基準法第108条ほか | |
| 10年 | 帳簿(仕訳帳、総勘定元帳他) | 会社法第432条 |
| 計算書類および附属明細書(B/S、P/L他) | 会社法第435条 |
上記の比較表の通り、文書の種類によって保存期間が異なります。また、法令で定められた期限はないものの、「株主総会議事録」や「取締役会議事録(役員会議事録)」など永久保管が必要とされる文書もあります。期限前に廃棄することのないよう、慎重に管理することが重要です。各種書類の保管期限について判断がつかない場合は専門家へ相談しましょう。
契約書の主な保管方法
契約書の保管方法は複数のパターンがあり、メリット・デメリットが異なります。それぞれの特徴を把握し、自社に合う方法を検討しましょう。
紙で保管する
紙の契約書を保管する際は、ファイリングして書庫で整理整頓することが基本です。取引先企業名で分類して五十音順に並べる、日付順に並べるなどの管理方法を決めておきます。
紙の契約書は、電子データのように気軽に書き換えられる心配が少ない点がメリットです。一方、近年は高度なセキュリティ対策が施された電子契約システムを利用する企業も多く、改ざんや偽造などのトラブルを電子的に防ぎやすくなります。
また、電子機器の扱いに慣れていない従業員にとっては、紙の契約書管理のほうが容易に感じられるケースもあります。しかし、紙の場合はどこに何があるのかを把握しにくく、電子保管と比べて検索に時間を要することも少なくありません。加えて、用紙代や保管コストなどもかかる点に留意しましょう。
紙をPDF化して保管する
紙の契約書をスキャンし、PDF化したうえで保管する方法があります。電子データ化することで紙媒体より検索・閲覧しやすくなる点がメリットです。保管スペースを削減できるため、保管場所の確保に困っている場合にもおすすめです。物理的な紛失リスクも軽減できます。
PDF化を実施する際は、データ保存のために書類を一つひとつスキャニングする手間がかかる点を考慮しましょう。スキャンデータの運用方法についても、社内で一律のルールを定めたうえで運用していくことが求められます。
また、法律上、紙の契約書しか認められていない書類も存在します。そのため、すべての契約書をPDF化して原本を廃棄できるとは限りません。例えば、以下のような書類は電子契約が認められておらず、紙の契約書を交わし、紙のまま保管する必要があります。
・事業用定期借地契約
・企業担保件の設定または変更を目的とする契約
・任意後見契約書
電子契約書で保管する
電子契約ツールの導入で契約業務のペーパーレス化を進め、電子データとして契約書を作成・締結する方法があります。契約書はサーバーやクラウド上に保管でき、郵送代や印紙税、コピー代といったコストもかかりません。
電子契約なら書面のやり取りにかかる時間を削減し、検索機能で必要な情報が簡単に見つかるので、効率的に契約関連の作業を進められるのも魅力です。担当者の業務効率化につなげられます。
ただし、電子契約を開始する際は、取引先からの理解が必要です。電子契約を交わすためには、相手方にも電子署名を求めることになります。企業によっては導入が難しく、引き続き紙の契約書を要求するケースも見られます。
上記のようなパターンでは、電子契約と紙の契約書を併用することになります。異なる形式の契約書は管理が煩雑になる傾向にあるため、一元管理可能なツールやサービスの導入も視野に入れましょう。
外部機関に委託する
重要書類の保管や管理を請け負う外部機関に依頼し、契約書を保管するのもおすすめの方法です。書類管理のノウハウを有しているサービスなら安心して一任でき、自社内での管理の手間を省けます。セキュリティレベルや防災面で安全性の向上も期待できます。
書類保管サービスは業者によって料金が異なります。契約書の量が多いほどコストも増大するケースが少なくありません。詳細な条件を伝えて見積もりを取り、初期費用やランニングコストを把握しましょう。
契約書の保管期間に関してよくある質問
契約書の保管期間に関連する、よくある質問や回答をご紹介します。気になる疑問を解消して契約書の適切な管理を行いましょう。
Q1.保管期間を過ぎた契約書の処理方法は?
保管期限の過ぎた契約書は、適切な方法で処理することが重要です。紙の場合、一般的には自社でシュレッダーにかけて処理するか、廃棄物専門の業者に委託して処分します。 処理方法を誤ると情報漏洩のリスクが高まり、法的な問題に発展する可能性があるため注意が必要です。例えば、目の粗いシュレッダーにかけてしまうと契約書の復元が容易になり、機密情報が流出してしまうリスクがあります。専門業者へ委託する場合も、信頼できるサービスを選ぶことが重要です。
Q2.保管期間内に契約書を誤って廃棄してしまった場合どうする?
保管期限の過ぎていない契約書を廃棄すると、罰則が科せられるおそれがあります。故意ではない場合も関係なく、法人税の追徴課税を徴収されるケースもあるため注意が必要です。
Q3.永久に保管すべき
法律上の決まりはないものの、永久保管したほうが良いと考えられている契約書もあります。例えば、契約内容の効力が存続している契約書や、特許・商標などの知的財産権に関連する書類、社内規則に関わる書類などは永久に保管するのが望ましいといわれています。
Q4.保管期間を過ぎても契約書を廃棄しなかった際は罰則がある?
基本的に、契約書の廃棄については法律上の決まりがないため、処分しない場合も罰を受けることはありません。ただし、契約書を廃棄せずに放置していると保管業務の管理コストも増加します。紛失や盗難による情報漏洩リスクもあるため、不要な契約書はすみやかに廃棄しておくと安心です。
また、例外としてマイナンバーの記載されている書類は、保管期間の終了後にすみやかに廃棄することが決められています。「確定申告書」や「給与所得の源泉徴収票」など、マイナンバー記載の書類の管理は注意が必要です。
契約書別の保管期間を守って正しく管理しましょう
契約書には法律で決められた保管期間があり、種類によってどの程度保管すべきかが変わります。契約書を交わした際は保存すべき期限についても確認しておくことが重要です。
契約書管理業務は煩雑な内容も多く、担当者の負担が大きくなることがあります。課題を解決するため、専門業者へ管理を委託するのもおすすめの方法です。文書管理システム「CLOUD CABINET」なら、紙の契約書と電子契約をまとめて管理できます。膨大な契約書も一括管理できるほか、必要な分だけスキャンして電子化するといった対応も可能です。機能やプラン料金などについて、どうぞお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
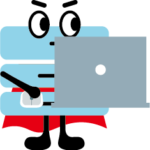
CLOUD CABINET編集部
文書管理に役立つ情報を発信していきます。 当編集部は、文書情報管理士・文書情報マネージャーなどの有資格者で構成されています!







